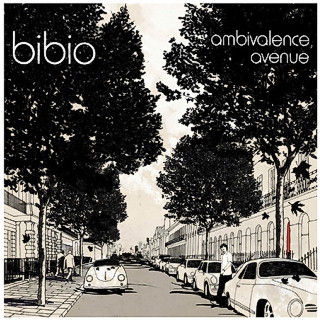日本でもお馴染みになるべきだった、アンディとエドのなかよしコンビ、1999年発表の三枚目。
前作では三名の歌い手をゲストに迎えたが、今回は〝例外〟除いて全てインスト。
M-01から彼ららしい楽しげなトラックが展開されるも、いつもとは質感がちと違う。
もったいぶらずとも答えは簡単。M-01、M-03、M-10でターンテーブリストがゲスト参加している通り、意図してヒップホップに接近したトラックもある。
もちろん〝もある〟というだけで、アルバム全体をヒップホップ色で塗り込めてしまうほど、彼らは新たな音の軸を欲していない。
あの広がりのある、メロディアスだけどどこか奇妙な音色使いの上モノさえあれば、PLAID以外の何者でもないトラックが出来上がるのだから。
聞こえは悪いが正直、毎回金太郎飴していただいても構わないくらいだ。
ただ、ちょっと……今回はPLAID節が僅かに弱いかな、と。
Warp二作目だし、いろいろ試してみようかな、とか。音色使いとか、テクスチャーとか。だからヒップホップのフォーマットを取り入れてみたのかな、と。
もちろんその試みが失敗とは思わない。成功ではなくて、ほんのちょっぴり他作品と毛色が違うってだけだが。
こんな作品もアリだと思う。男は度胸! 何でも試してみるもんさ。
こんな模索を初期に出来るのも、余裕のある証拠。下手打ってボロカスに罵られて消えた奴や、頭打ち状態で変化を求めて総スカン食らった奴などいくらでも居る。
機を見て敏なPLAIDって凄い! と褒め称えようぜ、みんな。
M-01 Shackbu
M-02 Ralome
M-03 Little People
M-04 3 Recurring
M-05 Buddy
M-06 Dead Sea
M-07 Gel Lab
M-08 Tearisci
M-09 Dang Spot
M-10 Pino Pomo
M-11 Last Remembered Thing
M-12 Lambs Eye
M-13 New Bass Hippo
M-14 Churn Maiden
M-15 Air Locked
冒頭で〝例外〟と書き記した通り、今回も豪華な歌い手、いらしていまス。
M-15終了後、無音を挿んでGOLDFRAPPのアリソン姫様がお忍びでお越しくださいました。お忍びですので、トラック名などございません。