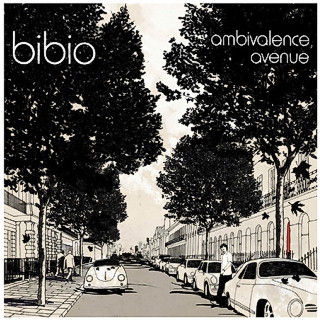毎度お馴染みFRIDGEのベーシスト、アーデム・イルハンのソロプロジェクト、2006年発表の二枚目。
いつも通りミキサーには同僚のキエラン・ヘブデン(イルハンとの連名)。レーベルはロンドンの大手インディーズ、Domino Records。レコーディングは簡素にイルハン家の倉庫、と普段通りの環境でリラックスして創られた作品。
――かと思えばちょっとだけ違う。あくまでちょっとだけ。
その〝ちょっとだけ〟を端的に言えば、〝いつもより凝っている〟。
本作は〝宇宙〟に関して語られたコンセプトアルバムみたいなものだ。
筆者はあまり歌詞には興味がないのでその辺は端折るとして、歌詞を伝えるべく歌を中心に据えた創りなのに、日本盤にすら(対訳どころか)歌詞カードが封入されていないのは如何なものかと。二倍以上の金を払ってわざわざ日本盤を買う必要があるのかと。
幸い、ADEMのHPへ飛べば全曲、歌詞が掲載されているので、興味があれば必読。
さて、問題は筆者が興味のある〝いつもより凝っている〟部分。
M-03は歌詞をAからZまで、Xをあえて除いて縦に並べ、単語を当て込んで意味のある歌詞にする手間の掛かりよう。それどころかコーラス代わりにAからXを除いたZまで並んだ単語の初音をサンプラーで取り込んでディレイさせ、イルハンの発声に併せて添える凝りよう。
それだけで筆者には鳥肌モノなのに、ハイライトは違う場所に配置されている。
M-05は通話不良を起こしたかのようなヴァイオリンが奥で鳴る一方、素朴なリードオルガンの音に導かれ、イルハンが情感たっぷりに歌い上げる名曲。ヴァイオリンが通話不良から復帰し、歌メロに添い遂げるサビは甘美の一言。
その他、アコギだけに頼らない豊富な音使いで感傷的にアルバムを進めていく。儚さはあるが暗さはない、ゆったりとしたトーンで。
その中でも、M-02、M-06、M-10で輪郭のはっきりしたビートを提供してくれるアレックス・トーマスの存在が光る。彼のお陰で〝ゆったり〟だけでなく小気味良さも生まれ、アルバムがより芳醇なモノとなった。(蛇足ながら彼は何とデスメタル上がりのドラマーで、現在はスクプなトムくんと行動を共にしている
最後に重要なコトを書くが、イルハンの歌唱が朴訥な雰囲気を残しつつも表現力が向上している点を見逃してはならない。歌という至高の音色を十分生かし切れている。
歌モノはこうでなくちゃね。
M-01 Warning Call
M-02 Something's Going To Come
M-03 X Is For Kisses
M-04 Launch Yourself
M-05 Love And Other Planets
M-06 Crashlander
M-07 Sea Of Tranquillity
M-08 You And Moon
M-09 Last Transmission From The Lost Mission
M-10 These Lights Are Meaningful
M-11 Spirals
M-12 Human Beings Gather 'Round